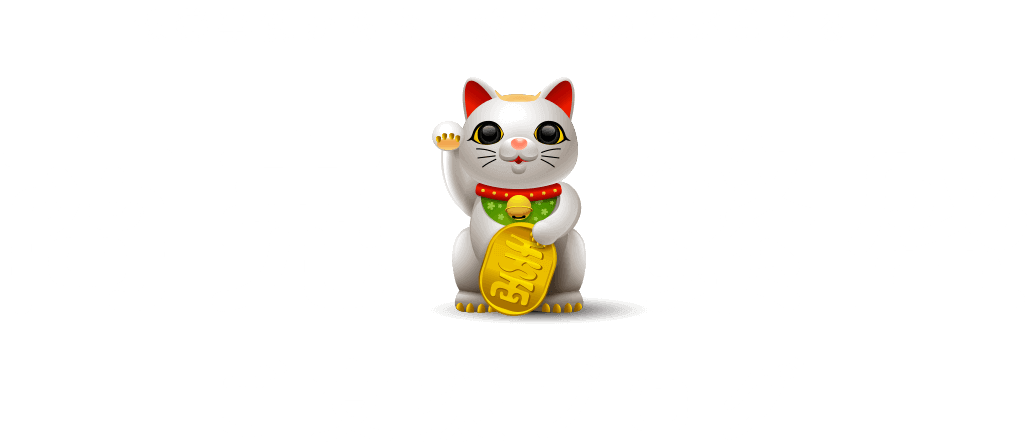2018.12.27
京橋白木の取り組み
《益子焼》有限会社 陶庫|つくりてを訪ねて Vol.6

物体の存在意義や方向性を模索し、「真の豊かさ」を模索する。
これからの益子焼への想いとは?
やきものの町「益子」において、益子焼の歴史や焼物の概念などを踏まえたうえで、人間がその文化をつくりだすという理念をお持ちの「有限会社 陶庫」代表取締役の塚本倫行さんにお話を伺いました。
なぜ焼物が売れなくなってしまったかを考える
ー本日は色々とお話を聞かせていただきたいと思います。
塚本 はい、よろしくお願いいたします。
ー作家の川崎萌展を開催されていますが、このような展示会は、陶庫さんの方からお声掛けされるんでしょうか。
塚本 そういうケースもありますし、作家さんの方からというケースもあります。
焼物は特殊なものなので、アートっぽく展覧会をやっていますが、実を言うと「工芸」なので道具としての機能が大事だと思うんです。
たとえば、絵画の場合は展覧会=発表の場となりますが、焼物は売上に直結させないといけないので、展示即売会という意味合いが強いですね。表現をしたいというつくり手のモチベーションとしても、展覧会は大切な場所だと思います。
ーものづくりで、実用性とデザイン性ではどちらに重きを置いていますか。
塚本 うちは完全に実用性を重視して、自社窯を中心に製造をしています。
昔は販売店も力を持っていたので、デザイン性重視で展覧会をやっていましたが、全量買い取りでほぼ現金払いでした。そうこうしているうちに、アート寄りの商品は売れなくなっていきました。
ー市場全体が減っていくような?
塚本 益子では1997年の94億円をピークに、市場規模は30億円弱にまで減ってしまいました。全国どこの焼物の産地でも同じようなことが起こっているのですが、なぜ焼物が売れなくなってしまったかを考えないといけないと思います。
当時は、表現性を重視するあまり、素材に力点を置かなくなってしまっていた時代でした。
益子だけでなく、有田も、瀬戸も、美濃も、その土地で採れた土や釉薬の原料を使っていたからこそ、その産地の文化だったのに「こういうのをつくりたい」という表現を優先させてしまった。
そのため、どこの産地の土でも買える現代においては、瀬戸の土を益子で使ったりして自の土を使わなくなっていきました。
うちの店でも「益子の土を使っていた商品は3割もなかった」ということもあったんじゃないかな。極端なことを言うと、うちの店と信楽の店の中身を取り換えてもわからなかったんじゃないかというくらいでした。

ーそんなことが起きていたんですね。
塚本 私の主観ですが、産地の特色をなくしてしまったことで、全国どこの産地で買っても似たような器が氾濫していき、陶器の市場が1/3まで縮小していったのだと思っています。
ーそういった過去の経緯から、今は実用性を重視しているのですね。
塚本 焼物の釉薬は木によって全然違うんです。たとえば、桜の木の灰と欅の木の灰では、木のもっている成分によって色の出方が大きく異なります。
私たちのプロダクトは、自社窯で益子の土と益子の釉薬、地の素材を用いて、安定供給できるようにしています。
ーものづくりで大事にしていることは何でしょうか。
塚本 焼物は「不易流行」。不易性より流行性が強いと感じています。
つまり、生活に密着したものなので、ライフスタイルが変われば大きさが変わっていきます。またその時代時代の流行もあります。
陶器に求められるニーズは、時代と共に変わるので、陶器はアートよりも工芸へ向かっていくと思うんです。焼物の場合は、必ず使う人の顔がみえる、日常使いのものだと。
ー事業を継がれた経緯についてお聞かせください。
塚本 東京の大学を卒業後に事業を継ぎました。姉が2人いて、私は末っ子長男でしたが、小さな頃からそういう「後を継ぐ、後継者」という環境がありました。
焼物業としては、昭和49年に始めたので私が2代目になりますが、もともとは肥料商を営んでいたので、そこから数えると4代目になります。
ここは、22年前に当時使っていた自宅を大幅にリニューアルしました。小さな頃は私も住んでいました。

ー商品開発はどのように進められているのでしょうか。
塚本 制作スタッフ3人と販売のスタッフとで、女性からの実用的な意見を聞きつつ、相談しながら進めています。
 蹴ろくろ 電動ではなく足でスピードを調整するので暖かみのある作品作りに向いている。
蹴ろくろ 電動ではなく足でスピードを調整するので暖かみのある作品作りに向いている。
ー伝統工芸である益子焼が続いていくために必要なことは何だと思いますか。
塚本 今のままだと確実に焼物文化はなくなってしまうと考えています。陶器というのは、どちらかと言うと、経済的にも精神的にも余裕のある人が使う道具だと思うんです。
益子では、台所道具として使っていたものが、食卓へ使うものへと移っていった。
経済が成長していた時代は、有田のような白物より、欠けやすい、重い、割れるような益子焼も使ってもらえたが、これから生活の中で今のまま伝統工芸ということに甘んじていたら、益子焼である必然性は無くなっていくと思います。

ー益子焼に携わる当事者の危機意識が必要とことですね?
塚本 これは益子焼だけの問題ではないと思いますが、陶器が売れた時代に業界関係者が勘違いしてしまったのではないでしょうか。
焼物は使用する素材が多すぎて、商標登録が難しいことも課題です。
以前は「とんかつと言えば益子焼」でしたが、美濃が益子焼風の美濃焼を磁器でつくったことで、一気に市場を塗り替えられたことがある。それほどコピーが蔓延している業界なんです。

今、益子には陶器市等のイベントもあって、年間200万人もの人が来てくれています。大きな数字ですが、それでも首都圏の人口の10人に1人でしかない。
これからは不特定多数の人を増やす売り方ではなく、特定少数の人に使っていただく、ファンを増やしていくということが生き残りの手段の一つではないかと考えています。
ー私たち京橋白木も、橋渡し役になれたらと思います!
塚本 こうした記事で露出度が増えれば、出会いも増えるんじゃないでしょうか?
今の若い人は、値段よりも、自分の気に入った空間で過ごしたいと思っているのではないかと思います。うちの商品を渋谷のお店で見て、わざわざ益子まで買いに来てくれた20代のお客さんがいたことは、印象深い出来事でした。

ー海外からの評価も高いと伺いました。これからの展望は?
塚本 つい最近、中国でセレクトショップをやっているバイヤーさんが来ました。
また、益子、瀬戸、信楽、京都、有田の5産地の白い釉で飯椀をつくるという、中川政七商店の「THE飯椀」という企画があって、私たちの窯で益子を担当させていただいたのですが、それを見たという香港のバイヤーがわざわざ来てくれたこともありました。
昨年は、パリのアトリエ・ブランマントでのプロデュースで展示販売会をやることになりました。2019年は1月のメゾンエオブジェに伝統工芸品として燕の金物とコラボレーションしたものを発表できればと思います。

ー海外での展開も楽しみですね、今日は本当にありがとうございました!
塚本 ありがとうございました。